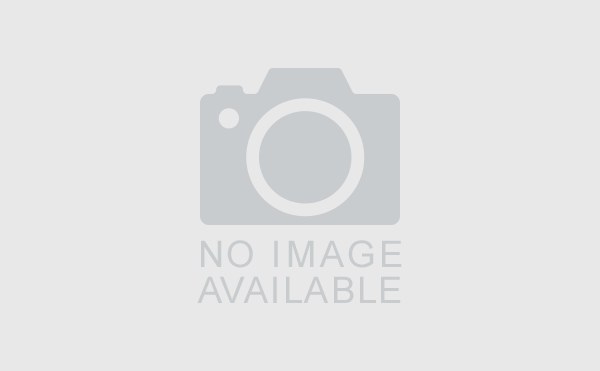なぜ狡猾なラーメン店が繁盛するのか?
道路! システム1刺激しまくってくるやんけ!
このあいだ車を運転してたとき、かように思うたのだ。
ダニエル・カーネマン著「ファスト&スロー」を読んでからというもの、考えごとをしてるとき自然にシステム1という単語が出てくる。
システム1とは何か?
カーネマンと彼の共同研究者が考え出した脳のはたらきで、直感や感情を司る、主に動物の本能だと思ってもらうと一番かんたんだろう。
さて、本題に入る。
「ラーメン」という単語を見たとしよう。
この文字は、美味しそうだろうか?
いや、美味しそうでもないし、腹も減らない?
否、実は、文字だけでも我々のシステム1は反応する。
システム1は、自動的に、かつ無意識に発動する。
自分では止められない。
例えば、赤ちゃんを見て不愉快になる人はあまりいない。
見て可愛いと感じるか感じないかは自分では決められないのだ。
さて、国道沿いに、とてつもなく大きなネオン看板に「ラーメン」とか「豚骨」とか書かれているのをあなたは見たことがあるだろう。
あなたはそのときそれを見てどう思った?(あるいは、どう感じた?)
「そういえば腹減ってるな」ではなかっただろうか?
それはあなたのシステム1が、ラーメン屋がしかけた網に引っかかったことを意味する。
これがシステム1が持つ性質の一つ、連想だ。
あなたの人生の中で、ラーメンという単語は「あたたかい」「おいしいもの」「麺」「こってり」という印象と深く結びついている。
そのため、見た瞬間、自動的にこれらのイメージが想起され、
食べたい、という気持ちになって現れる。
さて、システム1を抑えこむためには自己制御できるだけの精神エネルギーの残高が必要なんだが、
国道を通るとき、いつも残高が十分とは限らない。
たまたま残高が足らないときには、あなたは店の中に引きずり込まれることになる。
これでラーメン店の目的は達成された。
彼らは、看板を見た人を100%の確率で店内に引きずり込もうとはいささかも思ってないことにも注意しよう。
ところで我々の脳にはシステム1に対して、システム2というはたらきも存在する。
これも先ほどのカーネマンとトヴェルスキーの考え出した概念だ。
感情や直感のシステム1に対して、システム2は論理思考を司る。
例えば「あそこにラーメン屋があるな。でも今月は節約しなきゃいけないからやめとこう」
という思考のプロセスだ。
これは、自動的ではなく意識的にはたらかせないといけない。
かつ努力を要するという特徴もある。
つまりエネルギーが必要なんだな。
じゃあシステム1が網にひっかかっても、システム2が止めてくれるから大丈夫なんじゃないの?
と思うむきもあるかもしれない。
さよう、システム2は本来そういうはたらきをもつし、かつ、そう期待されている。
しかしかなしいかな、しばしばシステム2はシステム1を擁護するためにはたらいてしまうことがある。
例えばこうだ。
「今日は仕事で頑張ったから、ラーメンだ」だとか、
「今日はあんな良いことがあった。気分が良いからラーメンだ」だとか
「今日はあんなイヤなことがあった。気分が悪いからラーメンだ」だとか、
つまりシステム1のわがままを実行するもっともな理由をシステム2が考え出してしまう。
かくして、
ラーメンはうまいが、システム1の刺激がうまくない、こだわりの店が閉店し、
ラーメンがうまくないかわりに、システム1の刺激がうまい、狡猾な店が生き残る。
したがって国道沿いにはシステム1を刺激するものが溢れかえるというわけだ。
今ボクは、システム1への刺激に抵抗する努力をしている。
決めた店以外では、絶対に外食はしない。
網に引っかかりそうなときはシステム2を呼び出し、
「家に帰って何か作ったほうが美味しいし、安くあがる」
と考える。これでどうにかなることが多い。
とはいえこれでどのくらい抵抗できるものやら。
容易ではないぞ。
なぜならシステム2は怠け者だからだ。
今後も、戦いは自分の思うとおりには運ばないかもしれない。
この手ごわい敵たちに対して、いまだ有効な戦略が見つかってないというのが現状だ。