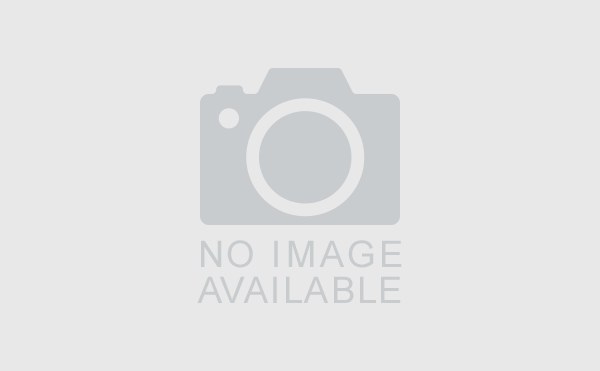難しい問題は放置が最善手
ちょっと考えてわからんかったら答え見てエエでー。
と、ウチの教室では生徒のみんなにそう言ってるの。
あんまり自力の解決にこだわりすぎると、次に勉強するのがイヤになると思うから、ってのが理由の一つ。
あと一つの理由は、ほっといたらそのうち勝手にわかるようになることがよくあるから。
というのも。むかし高校の理論化学の食酢の中和滴定の問題で
問題: 共洗いするのはどの実験用具ですか?
答え: ビュレットとホールピペット
というのがあった。
理由は容器の中に水滴が混ざってたら濃度が変わってしまうから、なんだけど、
まて、じゃあコニカルビーカーはどうして共洗いしなくていいんだ?と疑問に思って、吐くほど一生懸命考えたけど全然納得できなくて。
結局あきらめて、1年以上たってから、もう1回考えてみたら、ああそうか、と。
あっさりわかった。
もし共洗いせず水滴が残るコニカルビーカーに、体積を測り取った食酢を入れた結果、食酢の濃度が小さくなっても、問題はない。
なぜなら、ホールピペットで体積を測り取った食酢が、コニカルビーカーで薄まっても、酢酸の物質量、ひいては水素イオンの物質量は変わらない。
よって、食酢がうすまってもうすまらなくても、中和に達するまでの水酸化ナトリウム水溶液の滴下量は変わらない。
したがって、コニカルビーカー内の水滴は、食酢の濃度を調べる障害にはならんじゃないかと。
3分くらい考えただけでわかった。
ちなみに、ビュレットとホールピペットで扱う溶液は、濃度が重要になるから、共洗いが必要なんだね。
1年前にあんなに一生懸命考えたのは何だったんだと馬鹿らしくなったものよ。
教訓。何かわからんことがあったときにやっちゃイカンことは
一生懸命がんばる
ことではないでしょうか。
三国志演義でも諸葛孔明が北伐のときに、言うとったよ。
離が大事だとか何とか。
(離、は難しいことはいったん考えるのをやめる、とかいった意味らしい)