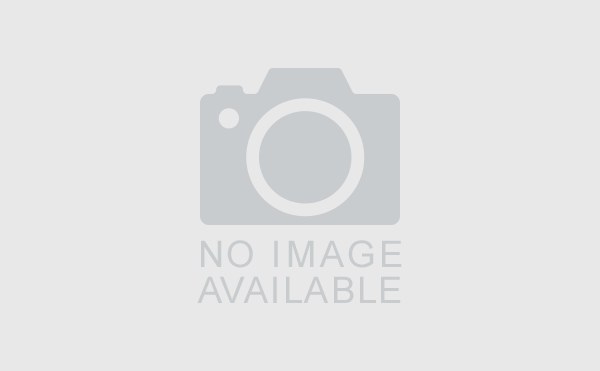勉強するのがキライ? ならばあなたは人間だ
ボクのお仕事は、学生のみんなに数学と理科を教えることなんだが、
違う言い方をすると、みんなからウルサがられるのが仕事だと思ってる。
どんなウルサイことを言ってるのかというと、
関数の問題はグラフを描いて考えたらどうか、だの
文章問題は絵を描いて考えたらどうか、だの
計算問題は、途中式を省いちゃダメよ、だの
x、yの増加量を聞かれてるときは、とりあえず変化の割合の公式を紙に書き出しておいたらどうか、等々。
さて諸君。これら全てに共通する点はなんだと思う?
それは「手を動かすこと」だ。
まあ、一般的にはこれを習慣にできれば学力は上がるとされてるし、ボクだけじゃなくどこの学校や塾でもよく言われてることだと思う。
しかしだ。
これを習慣化することは、よくよく考えれば容易ではない。
素直な子たちですら、何回も言わないとできるようにならないこともある。
結局できない(しようとしない)まま卒業してしまう子も少なくない。
なぜこんなにも、手を動かして考えることは難しいんだろう?
今ボクはこう思う。
紙に描いて表現するという作業は、人間の本性に反しているからではないかと。
この、紙にかいて情報を比較検討するときに作動する脳の部位は、たしか、
大脳新皮質の前頭前野、だったかな?
そしてこのような、紙に描いて情報を比較検討するためは、人の脳に努力を強いる。
これを人は好まない。
否、人の脳は好まない。
なるべくそういう努力はせずに済まそうとする。
なぜか?
脳を働かせるには、エネルギーが必要になる。
しかも他のどの器官よりも大量に消費する。
そして人はエネルギーを主に何から得ていたか、覚えてるか?
ブドウ糖だ。
今でこそ人類は、ご飯やイモから好きなだけブドウ糖を補給できるが、我々の先祖にとってブドウ糖はそれはそれは貴重なものだった。
無駄遣いは許されなかった。
だからなるべくブドウ糖の消費を抑えるようなメカニズムをもつ体をつくるための遺伝子が進化してきただろうことは想像に難くない。
それでいうと、グラフを描いたり絵を描いたり途中式を丁寧にかくなんてことは、ブドウ糖をひどく消費することで、
つまり子ども(や大人)が勉強がきらいというのは至極もっともなことで、むしろ勉強が習慣になってる子のほうが異例ではないかという見方もできよう。
だからある意味、われわれ学習塾の講師は、非常に難しいことを生徒のみんなに要求してることになる。
人間としての性質に逆らえ、と要求してるわけだから。
そう考えると、いまうちの教室の生徒のみんなはよく我慢してやってくれてるなと感謝する今日この頃ではある。