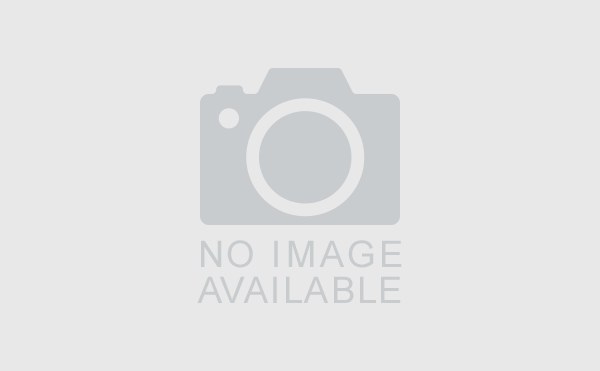司馬遼太郎にツッコミを入れてみる
かつて否の打ちどころがないように思われた、司馬遼太郎著作群ではある。
読み始めた当初は「なるほどね」と思ってた。
しかし最近ぼく、ダニエル・カーネマン著「ファスト&スロー」という本を読んだのね。
行動経済学の本なの。
内容は、どういう条件を満たしたとき人間は判断を間違えるかっていうのを体系的に解説した本で、爆絶名著。
さて、この行動経済学を学んだら、今まで完璧に思われてた、司馬先生の歴史考察にたまに穴があることに気づく。
今回それを指摘してみたい。
ではさっそく、司馬遼太郎著「翔ぶが如く」 文庫版9巻から。
当該箇所をざっくり要約すると、
西南戦争のとき、反乱鎮圧の政府軍(大久保利通側)に高島という人がいて、薩摩の反乱軍の補給路を断つ作戦を簡単に思いつきました。
でも司令官の山県有朋はぜんぜん気づけず、おかげで余計な戦死者をたくさん出しました。
だから、山県は軍を率いる才能は大したことなかったと思うんだよね。
司馬先生はこういう考察をしてるように思えた。
ところで行動経済学によると、何かしらを行ってるグループは、自分たちが行ってることの潜在的な問題に、当事者であるがゆえに気づかない、または(悪気なく)無視する心理的バイアスがかかるという。
外にいる人間のほうが、問題点がよく見えることがあるんだって。
そしてそのバイアスは人間の本能に属するものであり、回避するのは超むずかしい、とある。
それを踏まえると補給路を断つ作戦を思いついた高原さんは、当事者だったかもしれんけど、山県ほどの責任は負ってなかった。
つまり山県はいちばんバイアスに影響されやすい立場にあったとみることもできる。
だから「アンタ気づかなかっよね、じゃあアンタ才能ないね」は必ずしも正しいとはいえない。
この主張を妥当とするためには少なくとも、高原と山県を同じ条件で比べないといけない。
よって、人を評価するのってそんなに簡単じゃないね、という教訓が見える。
でも司馬先生はあれでいいのよ?
あの人は面白い本を書いて売るのが仕事だったんだから。
でもボクたちはふだんの生活で、あんまり早く結論だしすぎないほうがいいかもね、っつー話。